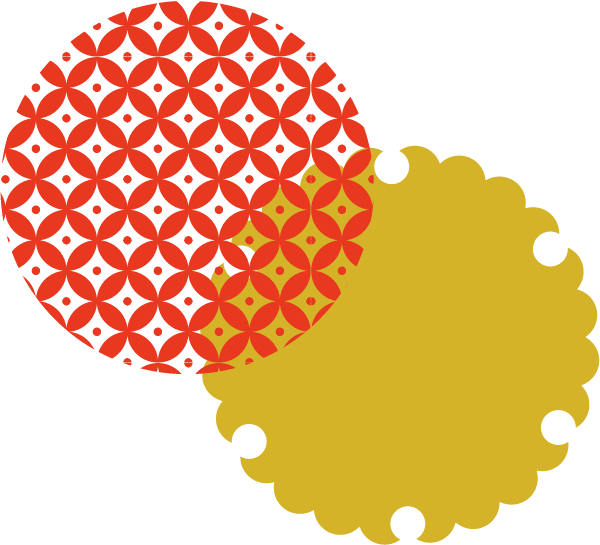所蔵 石川県埋蔵文化財センター
能登半島の製塩土器
- 公開状況
- 一部展示
- 時代
- 弥生時代終末期(3世紀頃)~平安時代(12世紀頃)
- 形態・種別
- 考古資料
- 地域
- 石川県珠洲市宝立町鵜島・三崎町宇治・大谷町、鳳珠郡能登町真脇、七尾市小島町・能登島えの目町・国分町、羽咋郡志賀町米浜
能登半島の沿岸部では、弥生時代から平安時代にかけて土器を使った塩づくり(土器製塩)の遺跡が約300ヶ所で確認されています。この塩づくりは、塩分濃度を高めた海水(鹹水(かんすい))などを土器に入れて、煮詰める方法で行われました。土器製塩は、弥生時代終わり頃から脚台付の土器(写真右下:七尾市小島西遺跡)を用いて始まり、古墳時代後期から平安時代には能登半島全体に広まりをみせます。底を棒状にした土器(写真右上・中央:珠洲市鵜島(うしま)遺跡など)や、丸底・平底の土器と土製支脚(写真左側:志賀町米浜(よねはま)遺跡など)を使って盛んに行われました。また、製塩土器は、粘土の接合痕をそのまま残すなどの粗いつくりで、鹹水を長時間煮詰めることから、火を受けた土器は赤くてもろくなっており、遺跡からは細かい破片の状態でみつかることが多いです。
本サイトに掲載しているテキスト・画像などのコンテンツ全般について、無断でのダウンロードやスクリーンショット、転用、転載等は禁止しています。

石川県の歴史と文化を伝える埋蔵文化財(遺跡)の発掘調査や出土品整理、報告書刊行を行うとともに、それらの成果を生かした展示や講座などを開催する開放型の施設として、1998(平成10)年に開館しました。
展示室には、テーマや時代別のコーナーなどがあり、県内各地の遺跡から発見された貴重な土器、石器などを見て、触れることができます。2001(平成13)年には、古代人の生活やワザをいつでも楽しく体験できる古代体験ひろばもオープンしました。
大人から子供まで、気軽に郷土の歴史を学びながら、文化財に対する関心と理解を深めることができます。
〒920-1336 金沢市中戸町18-1 Googleマップ
TEL 076-229-4477 E-mail daihyou@ishikawa-maibun.or.jp